速読スクール内で起こる出来事や、講師のプライベートなど、
適当に思いつくまま綴っています・・・気まぐれ三昧です、はい。。。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ジェフリー・アーチャー。
今日はこの作家の紹介です。
彼の作品は3つのジャンルに大別されます。
① 壮大なサーガ
② サスペンス・ミステリー
③ 短篇小説
この人のすごいところ。
とにかく、どれも優れている、という点。
サーガは文庫2冊という長さでも
時間を忘れてぐんぐん引き込まれてしまうし、
サスペンスものは、気がつくと登場人物とともに
ドキドキ・ハラハラを共有して、危険や困難に立ち向かってる自分がいるし、
短篇は洒脱で小気味よく、作品それぞれに感動やおかしみ、せつなさが込みあげます。
それらは、アーチャー氏の魅力を最大限に引き出した訳者、永井 淳氏の功績も
非常に大きいと思います。
永井氏の文章だから、ずっと安心して読んでました。
永井氏の死後、その世界観は戸田 裕之氏に引き継がれています。
短篇小説が好きな私ですが、
ジェフリー・アーチャーだけは常に別格。
最近のクリティカル・ヒット、2作品。
『ゴッホは欺く(上・下)』 新潮文庫
ジャンルとしては上記の②に属し、
芸術に造詣の深い彼ならではの作品。
聡明で勇敢なヒロインが大活躍します。
『誇りと復讐(上・下)』 新潮文庫
無実の罪で投獄されることになった男の物語。
さながら、現代の『モンテ・クリスト伯』。
ヤマ場てんこ盛り、というよりも、ずうっとヤマ場です。
最後の最後まで気を抜けません!!
それから短篇。
『十二の意外な結末』。
この中の一篇、『クリスティーナ・ローゼンタール』。
そして、『十二本の毒矢』の中の、『ある愛の歴史』。
素晴らしいの一語に尽きます。
本屋さんで、図書館で。
アーチャーの作品を見つけたら、
どれでもいいから手に取って読んでみてください。
それは必ず、当たりです。
長くなりましたが、最後に。
氏の魅力にとりつかれたら、ウィキペディアかなんかで
ぜひ経歴を調べてみてください。
今回のタイトルの意味が、お分かりいただけるかと思います。
PR
先日、NHKにて
100歳になられた日野原 重明先生の
ドキュメンタリーが放映されました。
先生は現役医師として、
ホスピス病棟で、緩和ケアに力を注いでおられます。
ご自身も、
92歳になる奥様の、進んでいく病状に葛藤しながら
患者さんの残された日々を見守っておられます。
ご自身の宗教的背景からか、
「愛」や「恩恵」、「使命」といった言葉が大変印象的でした。
どんなに痛みが激しくつらくとも、
先生の回診では、みなさん笑顔になります。
そして最期の最期まで諦めず、自身の生を全うする。
先生からの、若い医療従事者に対するメッセージは、
「死なない程度に病気しなさい」
そうすれば、患者さんの気持ちが理解出来るから、と。
6月に行われた前回の速解力検定では、
先生の著書から出題されていました。
この文章を読んで、私はますます先生のファンに。
特に、若い方たちに読んでもらいたいのは
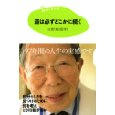
『道は必ずどこかに続く』 講談社刊
温かいユーモアに包まれた
生に対する真摯な姿勢に満ちた本です。
この世からいなくなった、大切な人を想い出すとき
その人はいつも笑顔です。
私も、願わくば
ユーモアとウィットに富んだ幸せな人生を全うできんことを。
100歳になられた日野原 重明先生の
ドキュメンタリーが放映されました。
先生は現役医師として、
ホスピス病棟で、緩和ケアに力を注いでおられます。
ご自身も、
92歳になる奥様の、進んでいく病状に葛藤しながら
患者さんの残された日々を見守っておられます。
ご自身の宗教的背景からか、
「愛」や「恩恵」、「使命」といった言葉が大変印象的でした。
どんなに痛みが激しくつらくとも、
先生の回診では、みなさん笑顔になります。
そして最期の最期まで諦めず、自身の生を全うする。
先生からの、若い医療従事者に対するメッセージは、
「死なない程度に病気しなさい」
そうすれば、患者さんの気持ちが理解出来るから、と。
6月に行われた前回の速解力検定では、
先生の著書から出題されていました。
この文章を読んで、私はますます先生のファンに。
特に、若い方たちに読んでもらいたいのは
『道は必ずどこかに続く』 講談社刊
温かいユーモアに包まれた
生に対する真摯な姿勢に満ちた本です。
この世からいなくなった、大切な人を想い出すとき
その人はいつも笑顔です。
私も、願わくば
ユーモアとウィットに富んだ幸せな人生を全うできんことを。
あまりにも書評欄で絶賛されていて、
タイトルに魅かれて読んだ一冊。
スティーブン・ミルハウザー 著 柴田 元幸 訳 白水社刊
淡々とした狂気。
異次元という現実にはまり込んだ人々の物語。
何かハッキリとした大きな事件が起こって…
という展開ではないからこそ、
疑問?という余韻が残る作品ばかりです。
実は、以前オリジナルで読んだことがあります。
英語の感想は、
無機質でモノクローム。
話の筋とは本来関係がなさそうな
風景の緻密な描写に満ちています。
具体的な感情表現はほとんどありません。
けれど、それこそが
うすら寒いような、何とも表現しがたい世界を醸し出しています。
それゆえすっきりとした読破感がなく、
名訳者、柴田氏の翻訳で読み直したのですが。
やっぱり印象が違いました。
日本語にすると、
ものすごく彩られた表現になっています。
(私が英語を理解出来てなかっただけ?)
表題作の 『ナイフ投げ師』 や
『新自動人形劇場』。
自分の芸を究め過ぎて、
その行き着いた先に幸福を見い出した人々。
しっくりと来ない居心地の悪さ。
マニア(というよりもはや信者?)は
その毒に冒されて、読み続けるしかないのです。
ミルハウザー氏こそ、
自らが創りだした世界の住人です。
本屋さんで、
子どもの頃に大好きだった絵本、見つけました。
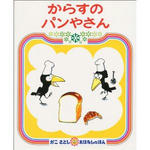
『からすのパンやさん』 加古 里子 著 偕成社刊
1973年に発行されてるんですね。
出てくるパンがこんがりおいしそうで、かわいくて。
あまりに懐かしくて、思わず立ち読みしました。
いたいた、4羽の子どもたち。
名前も面白かったよなあ~
なんて思って読んでましたが…。
子育てに追われて、
だんだんパンやさんが回らなくなって、
『びんぼうになっていきました。』
っていうくだり。
今まで全然知りませんでした。
大人になって感じられる、リアルな展開。
そんな場面はすっ飛ばして
おいしそうな絵ばっかりに見入ってたんでしょうね。
分かってなかったんだなあ、何にも。
せつなくなってしまいました。
ハッピーエンドだけれど。
そこに至る道には、
家族みんなの奮闘と、
お客さんみんなの声援があって。
(お店を盛り立てていくって、こういうことなんだなあ。)
秋にふさわしい色使い。
今の季節にぴったりの一冊です。
そして、私は今でもきっと
何にも分かっていません。
大人になったけど。
子どもの頃に大好きだった絵本、見つけました。
『からすのパンやさん』 加古 里子 著 偕成社刊
1973年に発行されてるんですね。
出てくるパンがこんがりおいしそうで、かわいくて。
あまりに懐かしくて、思わず立ち読みしました。
いたいた、4羽の子どもたち。
名前も面白かったよなあ~
なんて思って読んでましたが…。
子育てに追われて、
だんだんパンやさんが回らなくなって、
『びんぼうになっていきました。』
っていうくだり。
今まで全然知りませんでした。
大人になって感じられる、リアルな展開。
そんな場面はすっ飛ばして
おいしそうな絵ばっかりに見入ってたんでしょうね。
分かってなかったんだなあ、何にも。
せつなくなってしまいました。
ハッピーエンドだけれど。
そこに至る道には、
家族みんなの奮闘と、
お客さんみんなの声援があって。
(お店を盛り立てていくって、こういうことなんだなあ。)
秋にふさわしい色使い。
今の季節にぴったりの一冊です。
そして、私は今でもきっと
何にも分かっていません。
大人になったけど。


 」 と話してたら、
」 と話してたら、